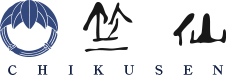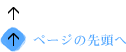小紋中形
藍が引き立つ粋な江戸前のゆかた
そのゆかたを見て、細かい点の文様が表裏合わさっているということは、実は着ている人以外は気付かないのかもしれない。そんな粋な文様が江戸っ子たちの心を掴み、当時から人気のあった「小紋中形」のゆかたは寸分違わず表裏に型付けを行うので、高度な技術が要求される。今となっては国内で唯一、この細かい点の文様の「小紋中形」の技術を先代から受け継ぎ現代に継承する小紋中形藍染工場の6代目の野口汎さんと7代目の息子の和彦さんを訪ねた。通常「長板中形」といえば線描きで柄を染出すが、野口氏は点で柄出しをする。それが「小紋中形」である。「小紋中形」の工程は大きく分けて2つ、型付けと藍染めがある。長さおよそ6m50cmのモミの1枚板に張った生地に、文様が彫られた約40cm角の型紙を用いて、生地に何回かにわけて糊を付けて型付けを行う。一度に片面しかできないので時間も手間もかかるし、表と裏の細かな文様を合わせるため高度な技術が必要である。しかし実際にその工程を目にすると、次々と流れるように型付けを行っていく和彦さん。受け継ぎ継承されてきた技術には無駄な動きがないと改めて感じる。藍染めの前に藍の定着をよくするために、大豆の搾り汁である豆汁を塗り1週間ほど寝かせてから、いよいよ藍染めに。藍甕の中で反物を捌き浸し、長年の経験から培われた「良い加減」で藍甕から反物を引き上げる汎さん。反物は空気に触れ酸化し始めると草色から藍色へ変化していく。藍が定着するまで乾燥させた後に糊を洗い落とし、晴天の日に干したら仕上がりに。この伝統技法を受け継ぎ伝えていくことは大変なことがたくさんあったはずだ。家族の支えがあってこそ継承されてきた技術なのである。6代目の汎さんに“和彦さんが後を継ぐ”とおっしゃった時は嬉しかったですか?と伺ったところ汎さんの笑顔の返答はとても印象的でその答えのすべてを物語っていた。残念ながらゆかたの着手が減っている昨今、だからこそ“本物”を感じられる親子の愛でつながった贅沢なゆかたをぜひ感じてほしいと思う。
【取材協力】小紋中形藍染工場 / 東京都八王子市
伝統技法“長板中形”の工程
-
「小紋中形藍染工場」
小紋中形藍染工場は幕末に開業。現在6代目の汎さんと7代目の和彦さんの親子で伝統技法を守り受け継いでいる。
写真は右が汎さん、左が和彦さんの作品。 -
「型付け」
継ぎ目がずれないように、また表裏のずれがないように、一型ごとに防染糊を置いていく。 -
「藍染」
藍甕の中で反物を捌き浸した後に引き上げ、空気に触れ酸化し始めると草色から藍色へ変化する。 -
「乾燥」
藍が定着するまで乾燥させる。 -
「水元」
手製の箒草の刷毛で防染糊を落とし、キレイな水に漬け、晴天の日に干したら仕上がり。
動画「型付け」
実際の型付けの様子。
継ぎ目がずれないように慎重に、かつ素早く型付けを行っていきます。
継ぎ目がずれないように慎重に、かつ素早く型付けを行っていきます。