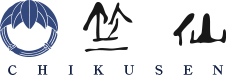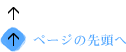浴衣の種類-生地-
特岡・コーマ・縮・紬・綿芭蕉・麻・絹紅梅・綿紅梅・奥州絣・綿絽
竺仙浴衣アイテム
コーマ白地、地染・コーマローケツ・コーマ玉むし・紬ゆかた・綿芭蕉玉むし
紅梅小紋・奥州小紋・縮小紋中形・絽小紋中形・絹紅梅小紋・麻小紋・絽長板・縮長板等
50アイテム、約1000柄
「長板中形(ながいたちゅうがた)」について長板中形は、江戸時代の浴衣制作技法でございます。
最近浴衣の照会の折、「長板中形」と書かれているお品を拝見します。しかし多くは残念ながら本物の長板中形とは異なります。長さおよそ三間半(約6m50cm)の樅(もみ)の一枚板に生地を張り、小紋よりは大きめの模様が彫られた中位の大きさ(約40cm角)の型紙を用いて、表と裏別々に糊置きを行い表裏の両面柄がぴったり合ったことを確認後に藍甕(あいがめ)で浸染染め(しんせんぞめ)を行った中形(浴衣)を指す言葉です。表裏の柄合わせがきちんとできていることを「裏が返る」と申し長板中形の真骨頂です。
くれぐれもお間違いにならぬようご注意申し上げます。
竺仙の浴衣も長板中形と申せるものは、ほんの一部でございます。
江戸時代から始まり、明治時代に大変流行した江戸ゆかたの主流です。
柄には絵師の描いた大柄ものと、昔の小紋型紙を利用した小柄のものがあり、江戸時代から伝わる、両面型付け浸染本藍染のおしゃれ着です。

- 長板に貼った生地の上から型付けを行う
- 12mの生地に型付けを行い生地を裏返し、裏から表の柄に会わせるように糊置きを再度行う。この時表と裏の柄がぴったり合わないと染めた後には柄がぼやけてしまう。
- 糊置きを両面施した生地を藍瓶の中に3回から5回位浸し染めあげます。(これ以上瓶に入れると糊が溶けてしまいます)
写真:全て2001美しいキモノ夏号より
藍染めは酸化により発色がすすみます。従って染上げられたばかりの一年ものは完璧に芯まで染まった状態ではありません。
出来れば1~2年空気に触れた品をお召しいただけると幸いです。
- オンラインショップはこちら▶
- 縮長板中形
明治20年代に始められた染料を注ぎ込む、手拭、ゆかたの独特な染色法です。
藍の注染ゆかたの絵際の美しさ。これぞゆかたと言われる所です。

- 木枠にはいった型紙で防染糊を置きます。
- 反物を型紙の大きさで折りながら(屏風だたみ)、糊置きを繰り返します。
- 糊置きの終わった反物を染色台の上に置き、
じょうろで染料を注ぎながら反物の下まで圧搾空気により浸透させている。
※写真1~3小学館'99サライ第11号より
注染は職人が1日数反しか生産できない時代、注染は当時としては、ゆかたを生産する画期的な方法と言われ、今でも夏物衣料として洗濯に耐えられる堅牢な染色法です。
「職人づくし」注染の記事へ▶︎
もともと型染を行ったり、無地染を行う際に使う刷毛染めのことですが、竺仙では紅梅小紋、奥州小紋の染色方法として使用しております。小紋染で使われるしごき染に比べ発色状態が美しい為、手のかかる引き染で仕上げております。

- 長板(約7m)に貼った生地の上に型紙を置き順次、糊置きを行う。
※写真:左/2001美しいキモノ夏号より 右/造形社'97男の隠れ家より

- 防染糊を置いた生地の上から引き染めを施す。
※写真:2001美しいキモノ夏号より
ゆかたというより夏の外出着というべき品です。
又、天然染料ではなく化学染料を使用している為、冷水で丸洗いできます。
ゆかたのように両面染めはしてございません。
「職人づくし」引き染めの記事へ▶︎
先染めとは、糸を染めてから織物に織ることです。注染、引き染などは、生地の上から柄を染める後染めですが、染上げた糸を使用し、織り上げた生地を先染ものといいます。先染めは 格子、縞、絣柄と幾何学的な柄が特長です。


- オンラインショップはこちら▶
- 麻着尺
染めの技法のひとつです。染料を混ぜた柔らかめな地色糊を、生地全体にしごきべらとよばれるへらで塗りつけて、地染めをします。生地の表面だけが染まり、裏は染まらず白色のままです。特に江戸小紋の染色にも使用されます絹紅梅小紋や、絹紅梅小紋絵羽などの地色を染めるのに用いられます。

- 生地をしごき台に移し、しごき糊をヘラでしごいていきます。
- 生地のしごき糊がお互いつかないように表面におが屑をまぶします。
- しごき終わった反物を蒸し箱に入れ、染料を定着させます。(季節や湿度、柄や色にもよりますが5分程)
- オンラインショップはこちら▶
- 絹紅梅小紋