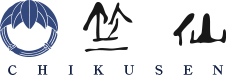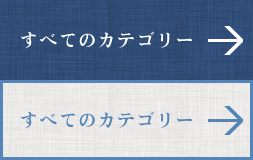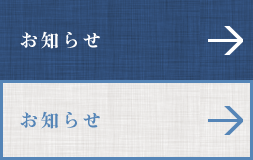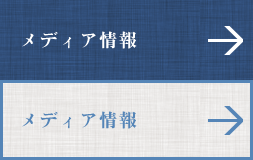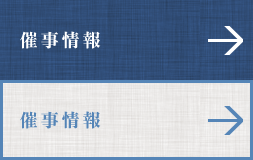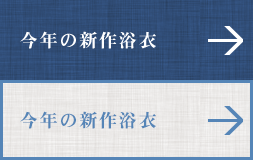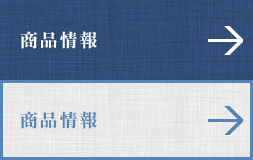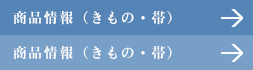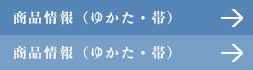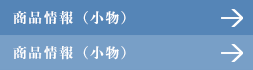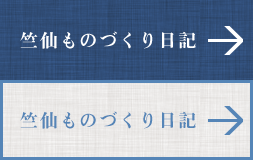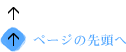2019.10.03 《10月の催事情報》
《10月の催事情報》
10月12日(土)〜20日(日)
大和富山店 5階呉服売場
10月19日(土) 江戸小紋ギャラリー
竺仙本店1階
10月23日(水)〜29日(火)
小田急百貨店新宿店 5階呉服売場
10月29日(火)〜11月4日(月・休) 第48回江戸・浅草まつり
高松三越 新館5階催物会場
2019.08.30 秋の催事情報
秋の催事情報
・9月4日(水)〜10日(火)
丸井今井:札幌本店 大通館9階 催事場
第43回 江戸老舗めぐり
※出品商品:絹布・綿布・小物
・9月8日(日)~23日(月:祝)
銀座:松屋 7階 呉服売場
※出品商品:絹布(江戸小紋・名古屋帯)
・9月12日(木)〜18日(水)
丸井今井:函館店7階 催事場
第37回 江戸老舗めぐり
※出品商品:絹布・綿布・小物
・10月29日(火)~11月4日(月:祝)
高松:三越 新館5階 催物会場
第48回 江戸・浅草まつり
※出品商品:絹布・綿布・小物
2014.05.12 ホームページをリニューアルしました。
ホームページをリニューアルしました。
ホームページをリニューアルしました。