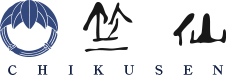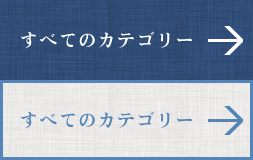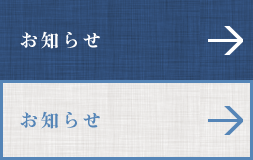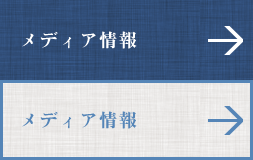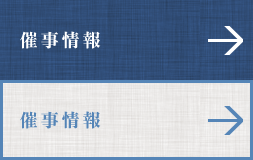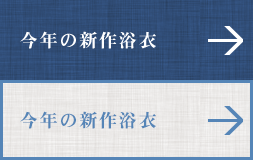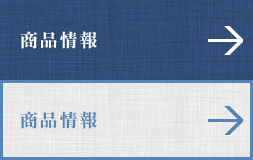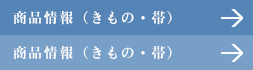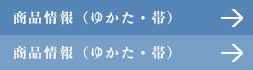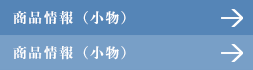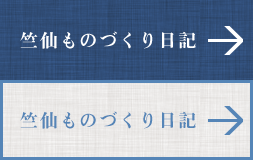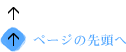2024.05.29 京都大丸「江戸老舗展」29日~6月4日まで
京都大丸「江戸老舗展」29日~6月4日まで
呉服売場に於きまして今年も江戸老舗展スタート致しました。
竺仙浴衣から竺仙江戸小紋を軸に数々のお品物ご用意致しました。
祇園祭りも、もうすぐでございます。
熱い暑い夏がやってまいります。
担当:近藤信之
2024.05.23 日本橋三越本店「#竺仙展開催中」5月22日~28日(火)呉服売場
日本橋三越本店「#竺仙展開催中」5月22日~28日(火)呉服売場
今年はパーソナルカラーをテーマにご自身がお似合いになるお色にあわせて竺仙展開催しております。
又日本画家宮下真理子氏が手掛けた美人三部作「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」をテーマに「竺仙奥州小紋」「竺仙綿紅梅小紋」「竺仙松煙染小紋」の染めで発表致しました作品をメインに展示販売しております。
5月25日(土)4階呉服売場 14時00分~ 宮下真理子氏と弊社代表小川文男のトークショーも予定しております。作品秘話を交えこの機会でしか聞くことのできないお話をさせていたきます。ご来場心よりお待ちしております。
担当:福本達也
2024.05.22 福岡岩田屋「江戸の匠展」竺仙出店しております。
福岡岩田屋「江戸の匠展」竺仙出店しております。
5月22日(水)~28(火)新館5階にて今年もスタート致しました。
今年の夏も猛暑になりそうでございます。
#竺仙のゆかたでその暑さを振り切って頂ければ何よりでございます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。
担当:山口勝己
2024.05.21 美しいキモノ 2024年夏号 発売中です
美しいキモノ 2024年夏号 発売中です

ハースト婦人画報社 『美しいキモノ 2024夏』 5/20発売になりました。
今年も竺仙のゆかたをたくさん掲載していただいております。
他にも江戸小紋など夏のきものの魅力満載です。
是非お手にとってご覧ください。
2024.05.16 久しぶりの竺仙ものづくり日記
久しぶりの竺仙ものづくり日記
今年の4月の平均気温は過去最高だったとか。
竺仙のある日本橋も5月に入って夏のような陽射しです。
5月は袷、6月と9月は単衣、7.8月は夏物・・といったこれまでの着物のしきたりが
最近の気温にそぐわなくなっているという声をよく聞きますが、今年は一層それを実感しています。
4月に透け感の無いゆかたを単衣の着物代わりにしてお出かけになったり、
暦を気にせずに気候にあわせて着物を楽しむ方が増えました。
こちらにも例年より早い時期から夏物の江戸小紋のお問い合わせをいただいており、
絹布商品部では単衣や夏着物にお勧めすることを意識して染め出しをすることが多くなりました。
絽縮緬 万筋
しぼのある縮緬糸で絽目に織られた生地 に縞が染められています。
絽縮緬は“単衣から夏物に代わる間のわずかな時期に着る贅沢なもの”と聞いたことがありますが、こちらの生地は縮緬のしぼが低く、比較的フラットに織られているので、最近では単衣から盛夏を通してお召しいただくようお勧めしています。
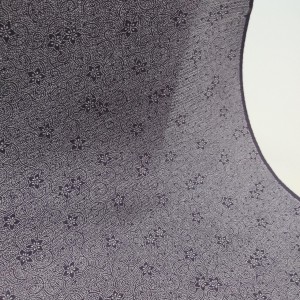
新潟県五泉で織られた駒絽生地に染めた桔梗唐草の江戸小紋。
型紙の錐彫りの細かな点がくっきりと浮かび上がり薄物ならではの繊細な柄の美しさが際立ちます。

こちらは強撚糸で織られた夏のお召し縮緬のようなシャリ感のある生地に、駒絽と同じ桔梗唐草の柄を染めました。
透け感が少なく、さらっとまとわりつかない肌触りなので真夏の前後にお召しいただきたい新しい生地の江戸小紋です。
実は職人さんにとって薄物生地は、染めるときに生地を通りぬけて板場についた防染糊を落としたり、生地裏もきれいに染まるようにいつも以上に気を遣うそうで、職人さん泣かせのお仕事でもあるのですが・・・
透け感のある夏の江戸小紋はひときわ美しいので
着用の時期が長くなって、よりたくさんの方に親しんでいただけたら嬉しいです。
2024.05.15 神戸・大丸「江戸老舗展スタート」5月15日~21日(火)最終日は17時迄
神戸・大丸「江戸老舗展スタート」5月15日~21日(火)最終日は17時迄
毎年恒例になりました、神戸大丸様での催事江戸老舗展スタート致しました。
浴衣は風の通り道が出来るお召し物としてこうして今も受け継がれた
日本文化、夏の風物詩でもございます。
「今年の夏も#竺仙のゆかた」でちょっとお出掛けしていただければ
何よりでございます。
竺仙のもうひとつの主力商品でございます「#竺仙江戸小紋と染帯」も
ご用意させていただきました。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。
例年と同じ7階中央イベントスペースにて展開しております。
担当:近藤信之
2024.04.27 2024年Vol.1店主が選ぶ今年の新作公開いたしました。
2024年Vol.1店主が選ぶ今年の新作公開いたしました。
4月~毎年月毎に4~5柄紹介させていただいております「店主が選ぶ今年の新作」
新しい風を感じて頂ければ何よりでございます。竺仙
2024.04.26 横浜・髙島屋竺仙展開催中4/24~30日(火)迄
横浜・髙島屋竺仙展開催中4/24~30日(火)迄
夏支度の季節、先陣をきり横浜髙島屋様で「竺仙展」開催中でございます。
ゴールデンウィークもすぐにやってまいります。
是非お出掛け頂きたくご案内申し上げます。
担当:山口勝己 山浦颯人
2024.04.03 名古屋松坂屋「江戸染色の老舗 竺仙展」開催中
名古屋松坂屋「江戸染色の老舗 竺仙展」開催中
4月3日(水)~9日(火)までの催事のご案内でございます。
江戸染め技術を継承し続け、今尚変わらぬ技術でお品物をお客様にお届けしております。
江戸小紋・ゆかた・染め帯を軸に美しい染めの数々をお見せできますよう準備致しました。
是非この機会にお立ち寄りいただきたくご案内申し上げます。
売場には竺仙スタッフが常勤しております。お気軽にお声掛け下されば幸いでございます。
担当:近藤信之
2024.03.29 竺仙ゆかた百貨店立ち上がり
竺仙ゆかた百貨店立ち上がり
今年の竺仙ゆかたの販売をスタート致しますお日にちのお知らせでございます。
日本橋三越 3月27日(水)
新宿伊勢丹 4月10日(水)
JR名古屋タカシマヤ 4月13日(土)
日本橋髙島屋 4月17日(水)
京都髙島屋 4月24日(水)
横浜髙島屋 4月24日(水)